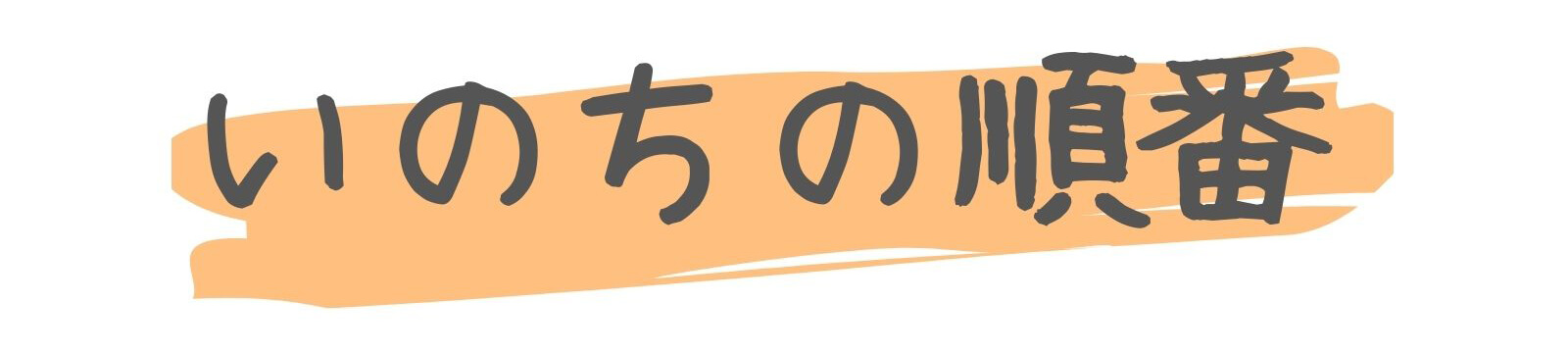- お墓が遠くて手入れができない…
- 先祖のお墓を見る人がこの先いない…
- 子供がいないから自分のお墓をどうしよう…
お墓には、このような問題がつきものです。核家族化が進んでいる現代では地方に住んでいる人も多く、実家の先祖のお墓を守れないと悩んでいる人もいるようです。
- また遺品整理をする場面になったときに、いちばん困るのも『お墓の問題』のようです。

簡単に処分できないし、放置することもできない…
この記事で分かること
- お墓を放置するとどうなるの?
- 管理ができなくなったお墓の対処法
管理ができなくなったお墓の、3つの具体的な方法を紹介します。すぐ読みたい方は こちら からどうぞ。
管理する人がいないお墓はどうなる?
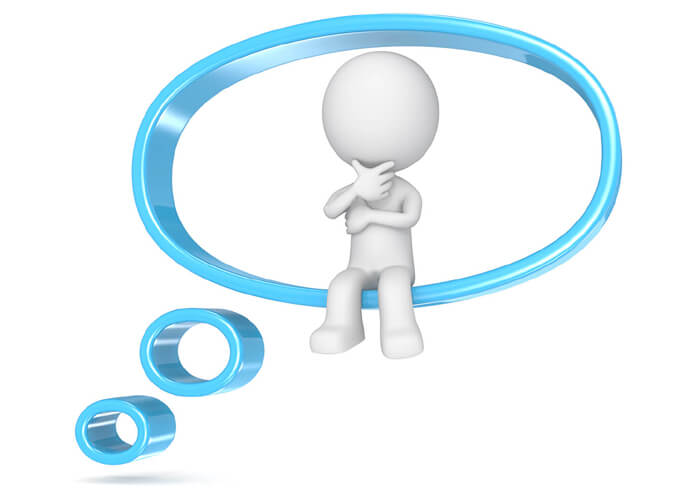
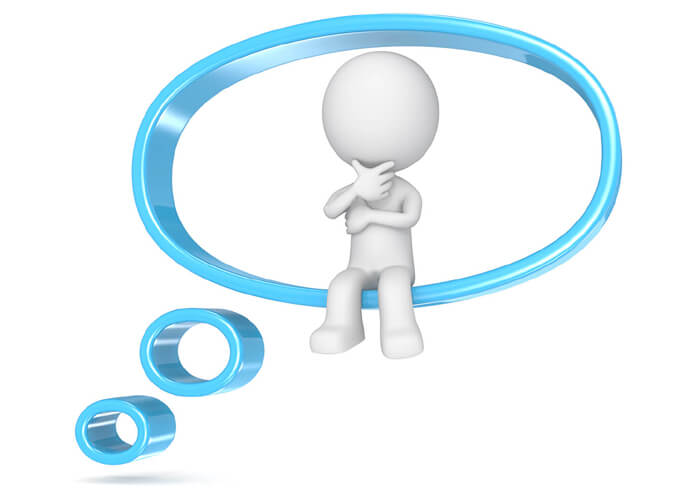
- お手入れができなくなったお墓は、当然ながら汚れていきます。雑草や木も生えますし、墓石にも苔がついていきますね。
建物などもそうですが手を加えてやらないと、どんどん荒れて汚くなっていきます。お手入れが行き届かず、荒れてしまったお墓のことを『無縁墓』といいます。無縁墓となったお墓の場合、管理費なども払われていないケースが多く、期間が長引けばいづれお墓は撤去されることになります。



お墓って放置すると撤去されてしまうの?
お墓を維持するためには維持費が必要。そのお金が払われなければ、当然ながら撤去されます。しかしすぐ撤去される訳ではなく、管理するお寺や霊園によってルールはさまざまなようです。
お墓が撤去されるまでの例
- 管理費を5年間滞納している場合
- 立て札や官報で警告をし、1年間連絡がない場合
このようなケースに当てはまると、撤去されてしまうようです。
【 官報とは 】
政府が発行する新聞のようなもので、休日以外は毎日発行される。自己破産などすると名前が載る インターネット版官報



でも撤去されると、遺骨はどうなるの?
お墓が解体されても、遺骨は処分されることはない!
ほとんどが敷地内にある『合葬墓』に埋葬されます。お墓は処分されても、遺骨が処分されることはありません。
【合葬墓とは】
一つの納骨室に、他の遺骨と埋葬するお墓のこと。
- 遠方などの理由からあなたがこの先お墓の管理ができないと感じたら、下記のような解決方法があります。
お墓の管理できない解決策
解説していきます。
お墓の管理ができない対処法①:墓じまい


墓じまいとは、文字通り『お墓を撤去する』ことです。
『お墓をなくすなんて考えられない!』と思うかもですが、継ぐ人がいなくなったらお墓を見る人はいなくなります。このような場合『お墓をなくしてしまう』というのも方法の1つになります。
墓じまいをする手順
- 親戚と話し合い
- 新しい納骨先を決める
- お墓の管理者に伝える
- 改葬許可証を取得
- 閉眼供養をする
- 石材店に連絡
- 遺骨を取り出す
- 墓石の撤去
それぞれ解説していきますね。
Step1 : 親戚と話し合い
まず『誰も見る人がいない!』からといって、独断でお墓を撤去するのはやめたほうがいいです。あとでトラブルに発展することもあるので、必ずはじめに親戚・親族に相談するようにしましょう。



もしかすると、お墓の管理をする人が名乗り出るかも!
基本お墓を継ぐ人というのは、親族になります。まずは長男や配偶者が継ぐのがほとんどですが、墓地のルールによっては
- 兄弟
- 姉妹
- 甥
- 姪
などでもお墓を継ぐことはできます。
また、親族以外の全くの他人でも墓石を継ぐことができるケースもあります。ようするに、隣の家の友人が継ぐこともできるということです。※お寺や霊園によってルールは異なる。



仲の良かった友人が継ぐこともできるのか…
- 『お墓が管理できない』と悩んだら、まずは親戚・親族に相談しましょう。思いもよらぬ人が手を上げるかもしれません。
Step2 : 新しい納骨先を決める
取り出した遺骨はそのまま処分する訳にはいかず、次の納骨先を決める必要があります。とはいえ『墓じまい』をしたいと考えている方だと、次の納骨先があるわけでないですね。
※クリックすると詳細へ移動します。
場所や距離が原因で、新しい場所にお墓を建てる場合はいいですが『お墓を建てる以外』にも納骨する方法はあります。それが下記の『手元供養』といった方法。
【 手元供養 】
手元供養とは、自宅や身近な場所に遺骨の一部(もしくは全部)を保管する方法。近年行われるようになった方法で、比較的新しい供養の方法。
墓じまいを考えている方もそうですが、お墓を持ってない人が新たに建てる必要もなくなります。遺骨を自分の好きなところに埋葬するのは法律で禁止されているのですが、必ず墓地に埋葬しないといけないわけでないのです。※遺骨を自分の家で保管することは、法律上問題ありません
自宅に置いて供養する以外にも、遺骨からアクセサリーを作って身に付けることもできます。『お墓や仏壇を持っていない』『田舎のお墓が遠くて管理できない』このような方にはおすすめな方法の1つで、近年は増加傾向にあります。
Step3 : お墓の管理者に伝える
- まずはじめに重要なことを書きます。
もしお墓がある場所がお寺の墓地の場合は、お墓の撤去をしたい旨を『決定事項』として伝えるのでなく『相談』という形で伝えるようにしてください。大事なことなので、もう一度いいます。
お墓を撤去することを『決定事項』として伝えるのでなく、あくまで悩んいるので『相談』という雰囲気で言うようにしましょう!
理由は、お寺の反感を買わないようにするためです。お寺にあるお墓を撤去するということは『離檀する』ということになります。
【 離檀とは 】
お墓の移転や撤去をして、お寺から離れること
お寺によっては『今まで管理してきたのに、簡単に離れるのか』と、離れることに対していい印象を持たないお寺も実際あるようです。本家から脱退するイメージでしょうか…、残された側は、いい印象を持たないかもしれません。それにより高額な『離檀料』を請求されたりと、トラブルになった事例も実際あります。
【 離檀料とは 】
お墓を撤去する時に、お寺に納める『お布施』のこと。
- とはいえ『撤去する・しないは親戚・親族が決めること』です。
あくまで撤去する旨の『伝え方』を、丁寧な表現で『相談がしたい』という姿勢で伝えるほうが、角が立たず良好な関係で終わらすことができるという話です。
Step4 : 改葬許可証を取得
- お墓から遺骨を移動させるためには『改葬許可証』が必要になります。
改葬許可証というのは『改葬(お墓の移動)を許可する証明書』といった意味。お墓じまい・お墓を移動させるときには必ず必要になってくる手続きになり、下記の書類が必要になります。
- 埋葬証明書
- 受入証明書
- 改葬許可申請書
- 改葬承諾書
※改葬承諾書の有無は、人によって異なります。
| 【 埋葬証明書 】 遺骨がこの墓地に納骨されているという証明書(墓地の管理者が発行) | 300円 ~ 1,500円 |
| 【 受入証明書 】 遺骨を受け入れるための証明書(次の納骨先の管理者が発行) | 基本的に無料 |
| 【 改葬許可申請書 】 自治体へ遺骨の移動を申請するための書類(役所が発行/役所のホームページから/郵送で送ってもらう) | 0円 ~ 1,000円 |
| 【 改葬承諾書 】 お墓の管理者とお墓の移動を申請したい人(改葬申請者)が異なる場合のみ必要な書類(墓地の管理者が発行) | 費用は未定 |
上記で紹介した『埋葬証明書・受入証明書・改葬許可申請書』を自治体に提出することで『改葬許可証』を取得することができます。(発行までに3日~1週間ほど)
【 メモ 】
改葬許可証を取得せずに遺骨を移動させるのはNG。
無許可で遺骨を移動さるのは、法律で禁止されています。罰金や拘留の可能性もあるので注意が必要。
Step5 : 閉眼供養をする
お墓から遺骨を取り出す前には『魂抜き』をする必要があり、これを『閉眼供養』といいます。
閉眼供養することにより、魂の宿っている墓石はただの『石』になります。必ず墓石を解体する前に行う必要があります。
Step6 : 石材店に連絡
墓じまいをするには、墓石を撤去する必要があります。自分で撤去することもできなくはないですが、とにかく重たく相当な力仕事になります。また墓石だけでなく、下の基礎部分も解体して更地に戻す必要があります。



個人でやるのは無理そうだな…
お墓を管理しているお寺などは、石材店との繋がりを持つところも多いので、きっと紹介してもらえるはずです。※お寺の決まった指定石材店がある場合は、そこに頼む必要があるので事前に確認が必要です。
もした指定石材店がなく、石材店を自分で探す必要がある場合はこちらの業者なども参考にしてください。全国にある優良な石材店から一括で見積もりが取れるサービスになります。複数の業者を比較できるので便利ですよ。
すべてのお客様にお墓を適正価格で【墓石ナビ】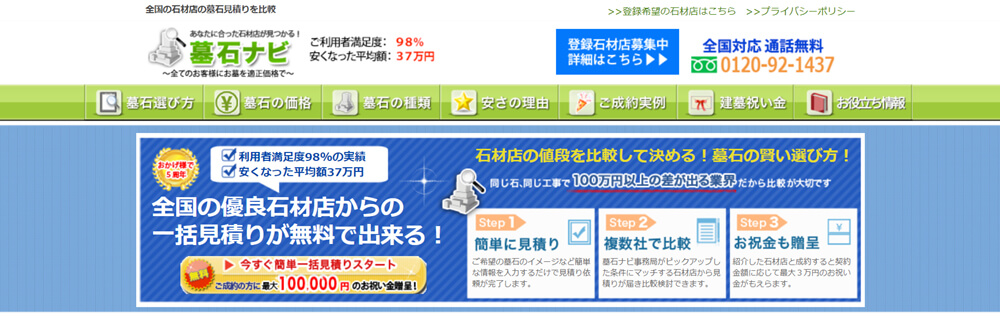
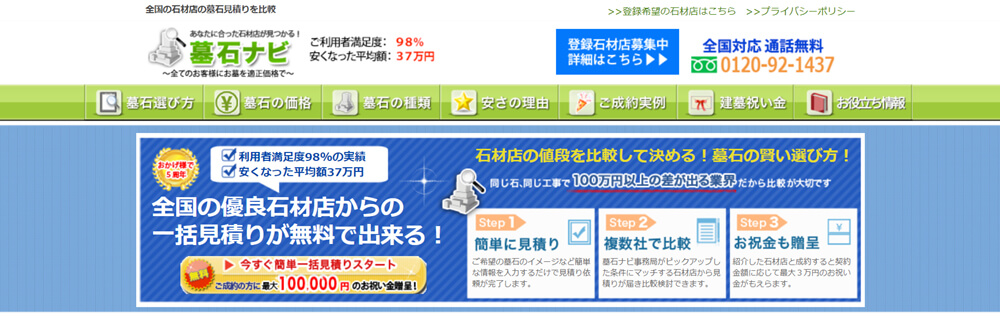
\ 公式サイトを見てみる /
Step7 : 遺骨を取り出す
- 遺骨を取り出す前には、事前準備が必要です。
- 閉眼供養
- 改葬許可証の入手
自己判断で遺骨を取り出すのはNG、きちんと手続きをしてから遺骨を取り出しましょう。また基本的に、遺骨は石材店の人が取り出してくれます。
Step8 : 墓石の撤去
- 墓地から墓石を撤去
- 墓石の基礎部分の解体
- 墓石の処分
この3つが、墓石の撤去になります。上記の項目だけであれば、費用はだいたい~30万円 (1㎡/約10万円) ほどになります。



基本的に『閉眼供養』をした後でないと、石材店は墓石を撤去してくれませんよ!
墓じまいにかかる費用
墓じまいにかかる費用には幅がありますが、おおよそ50万円~70万円ほどといわれています。幅がある理由としては、所有しているお墓の敷地面積が大きく関係してきます。
| お墓の撤去(お墓を更地に戻す) | 1㎡あたりおおよそ10万円ほど |
| お布施(閉眼供養) | 3万~10万円ほど |
| 離檀料(退去するお寺に払うお礼金) | 数万円~20万円ほど |
| 手続き費用(自治体やお墓の管理者の書類手続き) | ~2,000円ほど |
上記で説明した費用はあくまで『お墓を撤去』するまでにかかる費用です。そのため、次の納骨先にかかる費用は含まれていません。
お墓が山の奥にあるなど重機の使用が難しい場合だと、追加費用が発生する可能性もあります。また新しく準備するなら上記の費用とは別に、次の納骨先の費用もかかることになります。
墓じまいにかかる費用は次にお墓を受け継ぐ人が払うのが基本ですが、誰が払うといった明確なルールはありません。兄弟姉妹で均等に分割して払うケースが多いようですが、財産相続の割合から費用に差があることもあるようです。
- 【 親戚・親族 】まず最初に相談
- 【 自治体 】自治体によっては、補助金制度がある場合があります
- 【 銀行(メモリアルローン)】お墓や葬儀、仏壇仏具の費用に利用できるローン
墓じまいのメリット・デメリット
墓じまいをすることで、良い部分・悪い部分がそれぞれあると思います。ここでは、よくあるメリット・デメリットの例を紹介します。
- 子孫への負担軽減
- お墓の無緑化の防止
- 費用・管理面の負担が減る
- 次の納骨先によっては管理しやすくなる
- 費用が発生
- 『先祖の墓』がなくなる
- 地域特有の風習に反する可能性



メリットはいいですが、デメリットは事前に把握しといたほうがいいですよ!
墓じまいのトラブル
墓じまいをすることで、トラブルになることもあると思います。ここでは、よくあるトラブルの例を紹介します。
- 親戚・親族とのトラブル
- 管理者とのトラブル
- 石材店とのトラブル
【 親戚・親族とのトラブル 】
いちばんトラブルになりやすいのが、親戚・親族です。お墓に対する思い入れに温度差があると、特に多いようです。『先祖に対して無礼だと感じる人』と、『お墓の管理や費用の負担を減らしたい』の意見で、真向に衝突してしまうケースです。
意見が食い違ったまま墓じまいをしてしまうと、関係に大きな亀裂が入ってしまうこともあるので、きちんと話し合うことが大事です。
【 管理者とのトラブル 】
お寺などお墓を管理していた人とトラブルになるケース。こちらは上記で解説していますので、参考にしてください。【 お墓の管理者に伝える 】
【 石材店とのトラブル 】
墓石の撤去を自分で行うのは難しいので、石材店にお願いすることになります。金額の相場が分かりずらいので、高額な費用を請求される・工事が雑などのトラブル事例も実際あるようです。
うちの場合は墓じまいではなかったのですが、墓石の文字補修を依頼したときにあまりにも雑な作業だったようで、後日作業をやり直してもらったことがあります。遠方にあるので実際に見るまでかなり期間が空いたのですが、やり直してくれました。
昔からの付き合いがあったりお寺などに紹介してもらえる場合はいいですが、自分で石材店を探さないといけない場合は、このようなサービスもあるので参考にしてください。
- 厳選された優良石材店と多数登録しているので、トラブルになるのを減らすことができるはずです。
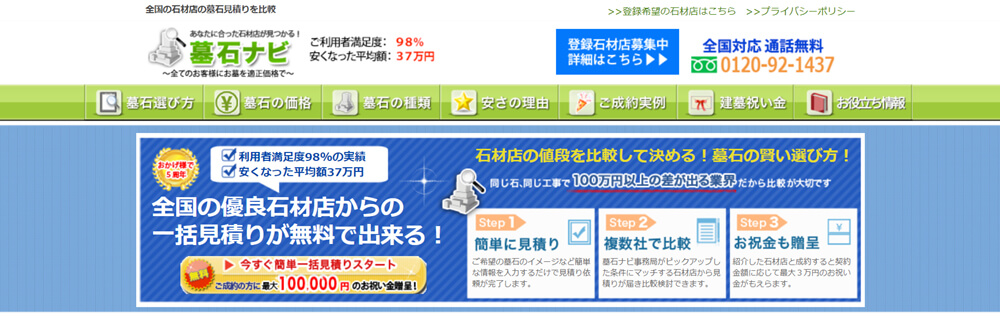
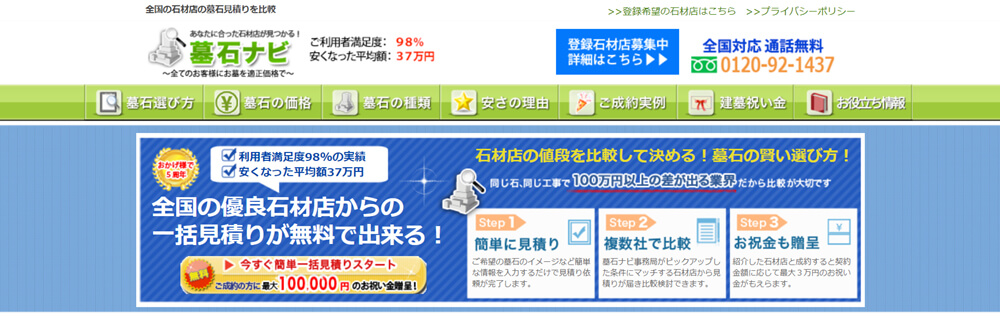
\ 公式サイトを見てみる /
お墓の管理ができない対処法②:永代供養


近年お墓の手入れ・管理ができない人は、とても増えているようです。
お墓の手入れ・管理ができない理由
- お墓が遠い
- 子供がいない
- 家庭を持った
少子化問題や核家族化が、背景にあると思います。また、子孫に費用や負担をかけたくないといった理由から、お墓を撤去したいと考えている人も比例して多いようです。
- そのような人のために『永代供養』という方法があります。



永代供養…?
聞き慣れない人もいるかと思うので、解説しますね。
永代供養とは
永代供養とは親戚・親族の代わりにお寺や霊園が、遺骨を管理・供養してくれる方法です。
永代供養と聞くと『永久』をイメージして、ずっと管理してくれると思うかもしれませんが、遺骨を安置する期間はある程度決まっています。
お寺や霊園によってルールはさまざまですが、節目になる『17回忌』『33回忌』『50回忌』を区切りとしている所がほとんどで、とくに『33回忌』に設定している所が多いようです。



期限が過ぎたら遺骨はどうなるの?
『期間が過ぎたら供養はしませんよ!』ではなく、違う形で供養されることになります。安置する期間がすぎた遺骨は、お寺や霊園の別の場所にある『合同墓』に他の方の遺骨と一緒に納められます(合祀型)。
- 『永代使用』といったよく似た言葉があります。似ているので勘違いする人も多いのですが、これは『永代供養』とは全く別の意味になります。
- 【 永代供養 】 永代にわたって、遺骨を供養・管理してもらう方法のこと。
- 【 永代使用 】 永代にわたって、お墓の土地を使用する権利のこと。
永代供養墓の種類【屋内タイプ】
遺骨を骨壷に入れた状態で安置しておく建物を『納骨堂』といいます。※納骨殿、霊堂ともいわれたりします。
納骨堂は屋内にあるので天候が悪くても楽にお参りすることができますし、管理者が清掃してくれるので掃除をする必要もありません。大きく下記の3種類に分かれます。
| 寺院納骨堂 | お寺が運営している |
| 公営納骨堂 | 県・自治体が運営している |
| 民営納骨堂 | 民間の法人が運営している |
- 棚式
- 可動式
- 仏壇式
- 位牌式
- 墓石式
- ロッカー式
このように分けられます。下記で解説しますね。
【 棚式 】
建物の壁・仕切りを利用して棚を設置、骨壷を納めることができる。納骨堂の元祖の方式。
【 可動式 】
建物内のお参りスペースに、専用カード・タッチパネルを操作することで、遺骨が機械的に運ばれてくる方式。マンション型ともいわれる。
【 仏壇式 】
各スペースが仏壇で分かれている。仏壇の下に数名分の骨壷を納めることができる。
【 位牌式 】
建物の壁・仕切りを利用して棚を設置し、位牌を納める方式。大きく下記の2つに分類されます。
- 位牌と別の場所に遺骨を置くタイプ
- 位牌と遺骨を一緒に置ける(中に入れる)タイプ
【 墓石式 】
屋内に普通の墓石と同じものを設置する方式。墓石の下に骨壺を納めることができる。
【 ロッカー式 】
コインロッカーのように扉が付いており、各スペースごとに分かれている。数名分の骨壷を納めることができる。
永代供養墓の種類【屋外タイプ】
- 合祀型
- 樹木葬
- 集合安置墓
- 永代供養付き墓
下記で解説していきます。
【 合祀型 】
ご遺骨を骨壷から出して多くの故人の遺骨を納める。他の人のご遺骨と混ざってしまうため復元することはNG。
【 樹木葬 】
シンボルとなる樹木を墓地内に植えて、骨壺やご遺骨を周辺の土の中に埋葬する。埋葬するたびに、新しい苗木を植える方法などもある。個別型と合祀型がある。
【 集合安置墓 】
他の方のご遺骨と同じスペースに安置するタイプで、大きな区画になっているお墓。ご遺骨が個別に納められているので取り出すことができる。
【 永代供養付き墓 】
お墓に永代供養をプラスしたもの。ご遺骨が個別に納められているので取り出すことができる。 一定期間(17回忌、33回忌など)が過ぎると合祀される。
永代供養墓の費用



やはりとても気になる!永代供養墓にかかる費用はどのくらいなんだろう?
さっくりした相場で話すと、10万~150万円ほどといわれています。魅力的なのは、一般的なお墓と比べると『永代供養墓』はかなり安く抑えられる点。
ちなみに一般的なお墓で、墓石を建てるタイプの場合の費用は、おおよそ100万円~350万円といわれてます。


- 墓石代:50万円~200万円
- 墓地代:40万円~150万円
- 管理費 (年間):4,000円~15,000円
もちろん立地・広さ・墓石の種類によって大きく異なるので、あくまで参考値にしてください。では永代供養墓にかかる費用を、下記でそれぞれ紹介していきますね。
- 棚式 : 5万円~10万円
- 可動式 : 80万円~150万円
- 仏壇式 : 50万円~150万円
- 位牌式 : 10万円~20万円
- 墓石式 : 100万円~200万円
- ロッカー式 : 20万円~80万円
※1人タイプ、家族タイプで費用は異なります。
- 合祀型 : 5万円~30万円
- 樹木葬 : 10万円~80万円
- 集合安置墓 : 20万円~60万円
- 永代供養付き墓 : 50万円~150万円
※1人タイプ、家族タイプで費用は異なります。
また上記とは別に、永代供養料(初期費用)・納骨堂の使用料(初期費用)・年間管理費が必要になります。
永代供養のメリット
永代供養にした場合、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。それぞれ調べてみました。
- 費用が安い
- 行きやすくなる
- 宗教を問われない
- 後継者がいなくてもいい
- お墓の管理を任せられる
- お寺との付き合いを問われない
下記で解説していきます。
【 費用が安い 】
墓石型のお墓を用意する場合は別ですが、それ以外の方法だと墓石を用意しなくていいので、費用を安くすることができます。
【 行きやすくなる 】
屋内におく納骨堂タイプだと、都心部のアクセスしやすい所にあることが多いです。今まで遠くにあってあまりお参りできなかった人だと、近くにあるのは便利かと思います。
【 宗教を問われない 】
永代供養にする場合、宗派は問われないことが多いようです。神道やキリスト教などでも特に問題ないようです。ただし、お寺・霊園の宗教に合わせた形で供養されることになります。
【 後継者がいなくてもいい 】
独身の方や子供がいなく次の世代に受け継げない方でも、お寺や霊園が管理・供養してくれます。
【 お墓の管理を任せられる 】
お寺や霊園が管理・供養してくれるので、家族の負担を減らすことができます。
【 お寺との付き合いを問われない 】
先祖からお寺の檀家に入っていると、お寺との関係を続けていく必要があります。具体的にはお布施や寄附をして、お寺の運営を支えることになります。
上の世代では法要や行事に熱心でも、自分達や下の世代が同じだとは限りません。永代供養することで離檀することができ、お寺との付き合いを問われなくなります。
【 檀家とは 】
『お寺に所属する家』といった意味。お布施などでお寺の運営を支えることで、優先的・手厚い供養を受けることができる家のこと。
【 離檀とは 】
檀家から離れること。
永代供養のデメリット
- 親戚・親族の理解
- 先祖のお墓を残せない
- 他人のご遺骨と一緒になる
- お墓参りのイメージと異なる
下記で解説していきます。
【 親戚・親族の理解 】
上の世代で『先祖代々のお墓を守る』という思考が強い方だと、お墓を持たない供養の仕方に抵抗がある場合もあるかもしれません。
受け継がれたものでなく、新しい形になることへの理解をきちんと得る必要があります。
【 先祖のお墓を残せない 】
永代供養のメリットは特定のお墓を所有しないことで、費用・管理面の負担を減らすことができること。
しかし、裏を返せば『お墓を持たない』ということなります。『先祖代々のお墓を守る』という考え方から外れることになるので、反対する人もいるかもしれません。
【 他人のご遺骨と一緒になる 】
永代供養は永久的なものでなく、期間が過ぎるとご遺骨は他のご遺骨と一緒に埋葬されます(合祀供養)
期間は『33回忌』を節目に設定している所が多いようです。他のご遺骨と一緒になるのに抵抗がある方だと、デメリットになるかもしれません。
【 お墓参りのイメージと異なる 】
墓石に水をかけ清掃し、花を供えてお線香をあげる。お墓に話しかけて霊園の中を歩く。うちのおばあちゃんがそうだったのですが、お墓参りを『趣味』としていたそうです。
永代供養の仕方によっては、従来のお墓参りとは異なる場合が多いです。お墓参りを日課とされている方がいる場合、話し合って決めるようにしてください。
永代供養をした後は?
永代供養をすると、お寺・霊園が墓地の管理や供養をしてくれます。最大の魅力が、この部分になります。では永代供養をお願いしたら、法要は個人で行わなくてもいいのでしょうか?



お寺に丸投げして、何もしなくてもいいの?
結論
しなくてもOK!ただ時間があるなら、やったほうがいい!
永代供養をお願いすると、お寺・霊園により異なりますが、下記のようなタイミングで供養が行われます。
- 【 春彼岸 】
- 3月の春分の日を中日とした、前後3日間
- 【 秋彼岸 】
- 9月の秋分の日を中日とした、前後3日間
- 【 月命日 】
- 亡くなった日と同じ日 (亡くなった日が4月5日なら、毎月5日)
- 【 祥月命日 】
- 亡くなった月日と同じ月日 (亡くなった日が4月5日なら、毎年4月5日)
- 【 年忌法要 】
- 定められた年の命日のこと(一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌・二十七回忌・三十三回忌)※3と7がつく年度
しかし個人でも法要することで、下記のようなメリットもあります。
- 追善供養できる
- 親戚・人とのつながりが深まる
【追善供養とは】
故人がちゃんと成仏できるように、生きている人たちが行う供養。
下記で解説していきます。
【 追善供養できる 】
お寺・霊園が行う供養だけでなく、親戚・親族も供養も行ってあげたほうが、亡くなった方も嬉しいはずです。冥福をちゃんと祈ることができます。
【 親戚・人とのつながりが深まる 】
法要は普段はめったに会うことのない親戚・親族・故人と親しかった人が、みんなで会える顔いい機会になります。
亡くなった方の思い出話や、知らなかったことなどもでてくるかもしれません。人と人のつながりや出会いは大切です。
お墓の管理ができない対処法②:散骨


よく『俺が死んだら、海に撒いてくれ』とかありますね。うちのお父も海が好きな人なので、もしかすると言い出すかもしれません。
海や山などに遺骨を撒くことを『自然葬』といいます。自然と一体化できるということで、生前から望んでいる方もいるようです。



いやでも、散骨って自分でやっていいの?
結論
散骨は自分でやってもOKです!
しかし、まず撒く場所が『自治体で散骨が禁止』されていないか、確認する必要があります。
散骨するには、骨を粉砕機で細かく砕く必要があります(直径2mm以下)。骨だと分かる状態で散骨すると、死体遺棄と問われることもあるので注意が必要。そして、よくある海や山に散骨する場合は下記のような注意点もあります。
【 自分で海に散骨する場合の注意点 】
海洋散骨は船で沖に出て、迷惑にならない海域でする必要がある。(沿岸漁業・養殖の迷惑になるため)
【 自分で山に散骨する場合の注意点 】
所有の土地・所有してる人の許可を得た土地でする必要がある。住宅が近くにある場合はNG。



できることであれば、業者に頼んだ方が確実です!
散骨がNGな場所
- 観光地
- 公園・住宅地
- 漁場・養殖場・防波堤
- 湖・沼・河川 (生活用水として利用されるところ)
人が普段から利用するような場所や、生活に関わってくるような場所で『散骨されている』と知ったらどうでしょうか?正直なところ衛生面でもさまざまな問題になりますし、民法で罰せられる可能性もあります。



個人で散骨することはできるが、かなりハードルが高い!


【みんなの海洋散骨】のような、ご遺骨のさまざまな供養に対応してくれるプロの業者もあります。もちろん『散骨』にも応えてくれますよ。
\ 公式サイトを見てみる /
ぜひ参考にしてください。